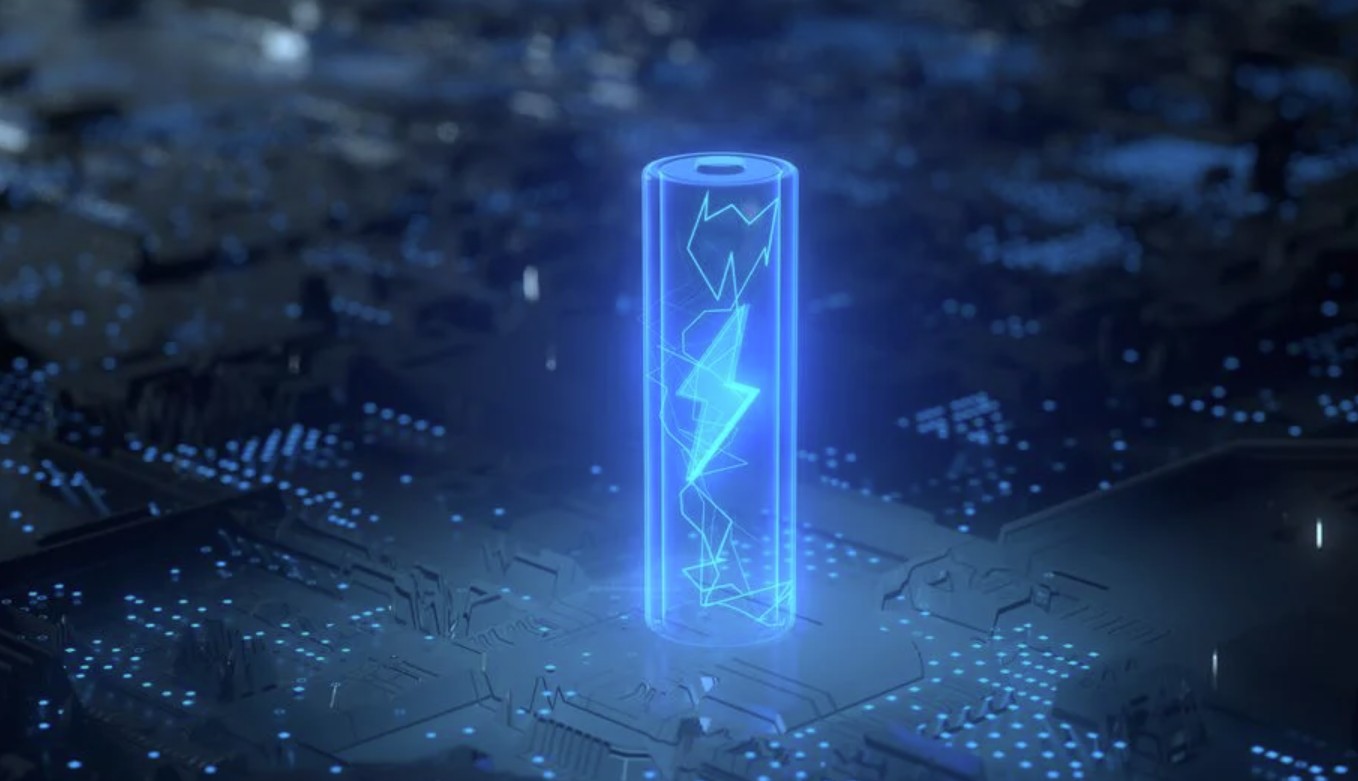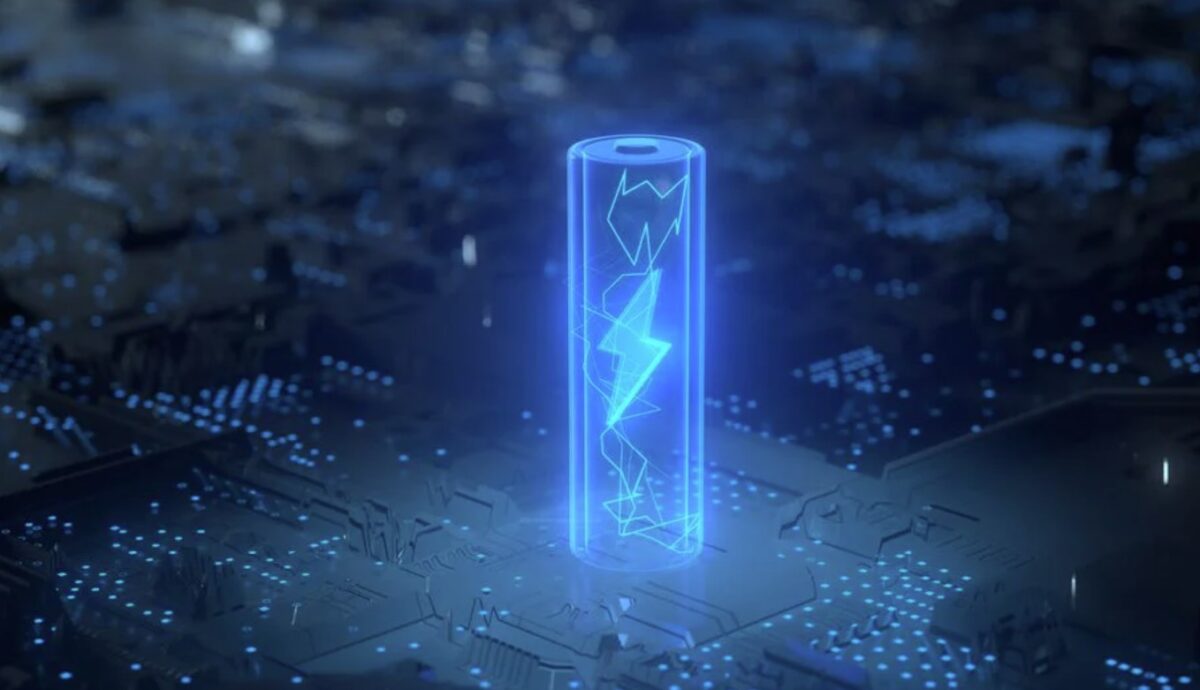
スマートフォンに搭載されるバッテリー技術は、年々進化を遂げています。その中でも近年注目を集めているのが「シリコンカーボン電池」。同じサイズでより多くのエネルギーを蓄えられるこの新技術は、いくつかの最新モデルですでに採用されていますが、SamsungのGalaxyシリーズやGoogle Pixel、iPhoneといった主力ブランドには、なかなか広がっていないのが現状です。
では、なぜこの優れた電池が、すべてのスマホに搭載されていないのでしょうか? 実は、明確な理由が2つあります。
シリコンカーボン電池の「魅力」
まず、シリコンカーボン電池の最大の特長は「高いエネルギー密度」です。つまり、これまでのリチウムイオン電池と同じスペースで、より多くの電力を蓄えることが可能になります。
たとえば、HonorのMagic VシリーズやOppoのFind N5といったフォルダブル端末では、驚くほど薄型ながら、大容量バッテリーを実現しており、その裏にはこのシリコンカーボン技術があります。
理由①:米国での規制が高いハードルに
第一の障壁は「輸送時の規制」です。
アメリカでは、1セルあたり20Wh(ワット時)を超えるバッテリーは「危険物」として扱われ、輸送や販売に厳しいルールが適用されます。例えば、Galaxy S25 Ultraの5,000mAhバッテリーは19.4Wh、Pixel 9 Proの5,060mAhバッテリーは19.68Whと、すでにこの基準ギリギリです。
一方で、10,000mAh以上のモバイルバッテリーが普通に売られているのを不思議に思う方もいるでしょう。これは「セル単位」での規制であり、複数のセルで構成される場合や、合計100Wh未満であれば例外として扱われます。
この規制を回避するために、OnePlus 13では6,000mAhのバッテリーを2つのセルに分けて搭載し、問題なく販売できているのです。
理由②:寿命と膨張リスクの問題
もう一つの、そしてより根本的な課題が「バッテリーの劣化と膨張」です。
バッテリー技術に詳しいエンジニアによると、シリコンカーボン電池は、リチウムイオン電池に比べて経年劣化が早く、2〜3年の使用で容量が大きく低下する傾向があります。
また、シリコン系の電池は充電時に大きく膨張する特性があり、ある研究では最大で400%も体積が増加すると報告されています。シリコンカーボンによってこの問題はある程度抑制されてはいるものの、従来の電池と比べれば膨張率は依然として高く、スマートフォンのような密閉された筐体では深刻な問題となりかねません。
それでも採用するメーカーの狙いとは?
では、なぜ一部のスマホはこの技術を導入しているのでしょうか? その答えはシンプルで、「スペック勝負で目を引くため」です。大容量バッテリーは、製品の魅力をアピールする武器になるからです。
ただし、賢いメーカーはそのリスクも理解しています。たとえば、Nothing Phone (3)は世界的には5,150mAhと公表されている一方、インドモデルだけは5,500mAhとしています。しかし実際には、どちらのモデルも物理的には同じバッテリーを搭載しており、あえて「制限」された容量表示にしているのです。
このように、あらかじめバッテリー容量をソフトウェアで制限することで、バッテリーの寿命や発熱リスクを抑える工夫が施されているわけです。これはOnePlusの一部端末でも見られる手法です。
将来的には普及の可能性も
シリコンカーボン電池は、技術的には非常に優れたポテンシャルを持っているものの、現時点では法規制や信頼性の問題が普及の大きな壁になっています。
ただし、研究は進んでおり、これらの課題がいずれ解消される可能性は高いと言えるでしょう。Nothing Phone (3)のように、ソフトウェアでの制限をかけつつ、実用性と性能を両立するアプローチは、今後のスタンダードになるかもしれません。
本格的な普及にはもう少し時間がかかりそうですが、スマホバッテリーの未来を担う技術として、シリコンカーボン電池の進化に注目していきたいところです。