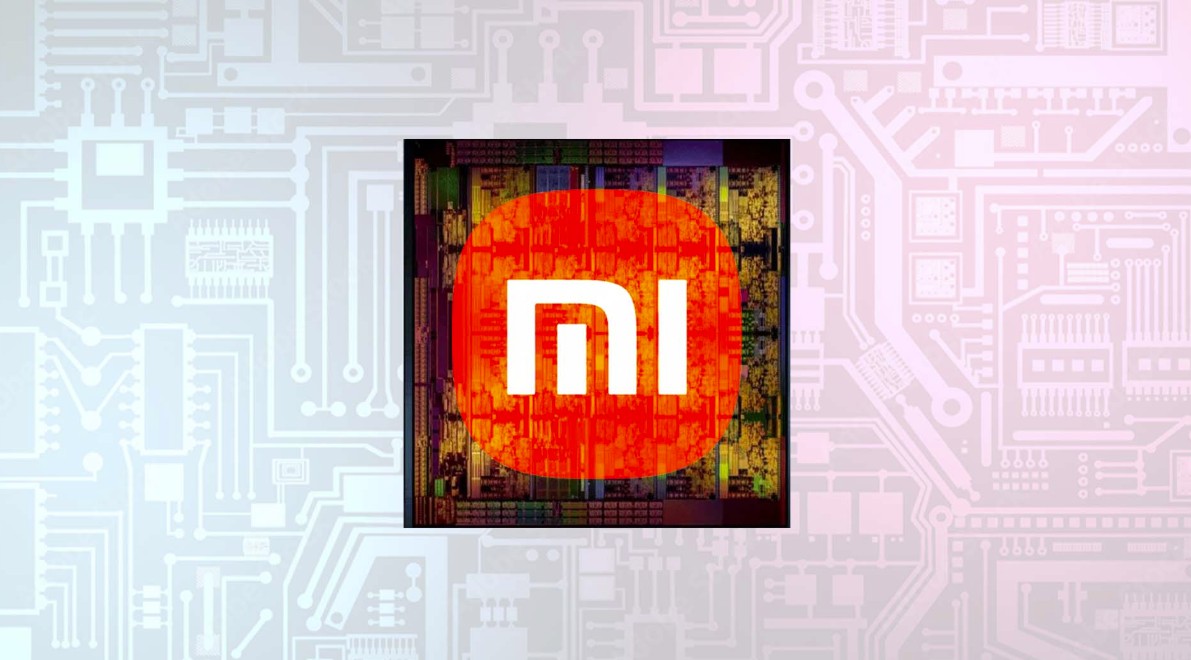
高騰する外部チップ依存からの脱却へ
スマートフォンの頭脳ともいえる「チップ(SoC)」の開発コストが年々上昇している中、Xiaomiがいよいよ自社開発への本格的な一歩を踏み出しました。クアルコムやMediaTekといった主要サプライヤーが最先端の製造プロセスへと移行する中で、調達コストが高騰。Xiaomiをはじめとするスマートフォンメーカーにとっては、こうした外部依存からの脱却が急務となっています。
こうした背景のもと、Xiaomiは自社チップの開発を専門に担う新たな部門を立ち上げました。そのトップには、かつてQualcommでシニアディレクターを務めた秦沐雲(Qin Muyun)氏が就任。社内でも重要プロジェクトとして位置付けられており、CEOの雷軍(Lei Jun)氏に直接報告する体制が敷かれるとのことです。
2017年の「Surge S1」以来、久々の本格挑戦
Xiaomiが自社製チップに挑戦するのは、実に8年ぶりのこと。2017年に発表された「Surge S1」では、TSMCの28nmプロセスを採用していましたが、その後は目立った動きはありませんでした。
しかし、ここ最近では3nmプロセスによるSoCのテープアウト(設計完了)に成功したという報道もあり、今年中の発表が期待されている状況です。ただし現時点では、3nmチップの製品化には至っておらず、今回の新部門立ち上げはその布石と見られます。
まずは4nmプロセスでの実績づくりへ
業界関係者によれば、XiaomiはまずTSMCの4nmプロセス「N4P」を用いたチップの開発に着手し、その性能はSnapdragon 8 Gen 1に近い水準になる見込みです。コアアーキテクチャにはARMの既存設計を採用し、自社独自コアはまだ搭載しないとされています。
この戦略には理由があります。最先端の3nmチップを一気に商用化するには膨大なコストとノウハウが必要であるため、まずは4nmチップで開発体制と技術力を磨き、その後の高性能モデルにつなげていくという段階的アプローチを取っているのです。
技術と自立性の両立を目指して
Xiaomiがチップの内製化に再び本腰を入れるのは、単にコスト削減だけが目的ではありません。今後、AI処理や高性能カメラ、5G通信といった分野での競争力を保つには、独自技術の確立が不可欠です。
今回の動きは、同社が「スマートフォンメーカー」から「テクノロジー企業」への進化を目指していることの象徴とも言えるでしょう。今後、Xiaomiがどのような自社チップを世に送り出すのか、注目が集まります。


