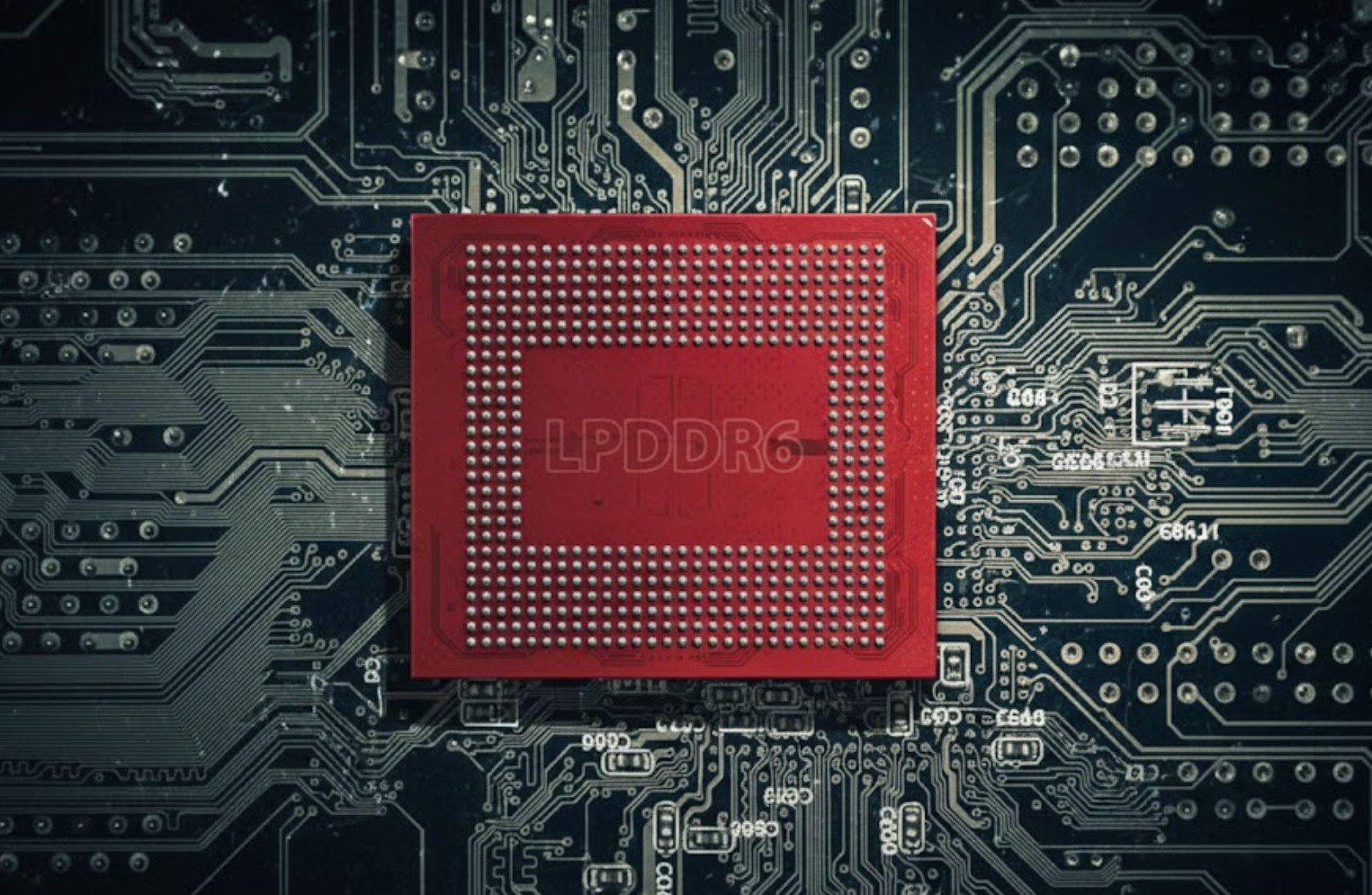ハイエンドスマートフォンの性能は年々向上していますが、その進化を真に活かしきれている機種は意外と少なく感じられます。そんな中、ZTE傘下のREDMAGICが投入した最新モデル「REDMAGIC 11 Pro」は、単に高性能チップを載せただけでは終わらない、ゲーマー向けの本質的な機能を実装しました。これらは、他メーカーも採用すべきと言いたくなるほどの内容です。
フレーム生成×AIアップスケーリングをスマホに
REDMAGIC 11 Proは、Snapdragon 8 Elite Gen 5の性能を最大限引き出すため、独自の液冷システムを搭載。この冷却性能により、長時間のゲームプレイでも安定した動作が期待できます。しかし真価は、冷却に頼って性能を引き出すだけではありません。

同機が備える注目機能は以下の2つです。
- AIアップスケーリング(画質向上)
- フレーム生成(補間によるフレームレート向上)
PCゲーマーにはお馴染みの技術ですが、スマホで両方を同時に実装した例はまだ珍しい存在です。
実際にタイトル「鳴潮(Wuthering Waves)」で両機能をオンにすると、スマホゲームとは思えない描画と滑らかさになり、クリエイターのDame Tech氏は「PCやPS5に近い感覚」と評価しています。
課題は「冷却」。 ベイパーチャンバーの限界が見え始めた?
ただし、両機能の使用にはCPU・GPU負荷が増し、端末の発熱も大きくなります。REDMAGIC側も機能使用時に警告を表示しており、冷却設計が必須であることを明確にしています。逆に言えば、この条件さえクリアできれば、多くの端末が同様の高いゲーム体験を提供できる可能性があります。
現状、各メーカーは大型ベイパーチャンバーに頼る傾向がありますが、すでに限界が見え始めています。たとえばゲーミング性をアピールするOnePlus 15は165Hzディスプレイを搭載するものの、Snapdragon 8 Elite Gen 5を3DMarkで動かした際に発熱でクラッシュしたと報告されています。
スマホゲーム市場が進化するには「本気の冷却設計」が必要
スマホ向けSoCは、PC級に近づいたにもかかわらず、ソフト面・冷却面の取り組みが追いついていないケースが多いのが現状です。REDMAGIC 11 Proが示した方向性は、「スペック競争」から「体験の最適化」へ。本来のゲーミングスマホが進むべき道を提示したと言えるでしょう。
今後、フレーム生成やAIアップスケーリングがAndroid全体に普及していくのか。そして各社が本気で冷却に取り組むのか。2026年以降のモバイルゲーミング市場の進化は、ハード・ソフト双方の取り組みによって大きく左右されそうです。